こんにちは!「コンビニぐらし」の木内澄也です。
コンビニ業界に20年以上従事し、店長としても多くのアルバイトスタッフの労務管理に携わってきました。
「バイトでも有給休暇ってもらえるの?」
「有給があるって聞いたけど、実際に取れるの?」
「申請したら店長に嫌な顔されそう…」
こうした相談を、私が店長時代に何度も受けました。
実は、アルバイトやパートでも条件を満たせば有給休暇は必ず付与されます。 これは労働基準法で定められた、すべての労働者の権利です。
ただし、現場の実態として「有給があることを知らない」「申請しづらい雰囲気がある」という声が多いのも事実です。
私が店長時代に経験した中でも、有給の存在を知らずに辞めていくスタッフが多くいました。 非常にもったいないことです。
この記事では、店長経験者の目線から以下について詳しく解説していきます。
- 有給休暇の付与条件と日数
- コンビニで実際に有給を取れるのか
- 有給申請の上手な伝え方
- 断られた場合の対処法
- 有給を効果的に使うコツ
有給休暇は、知っているだけで得をする重要な権利です。 給料日や深夜手当と同じように、自分の権利をしっかり理解して、損をしない働き方をしましょう。
コンビニバイトにも有給休暇はあるの?

アルバイト・パートでも労働基準法で有給は付与される
まず最初に、はっきりお伝えします。
アルバイトやパートでも、条件を満たせば有給休暇は必ず付与されます。
これは労働基準法第39条で定められた、すべての労働者の権利です。
「正社員だけの制度」「フルタイムじゃないともらえない」というのは完全な誤解です。
私が店長時代、面接や研修の際に「バイトにも有給があります」と説明すると、ほとんどのスタッフが驚いていました。
「え、バイトでももらえるんですか!?」
「知りませんでした…」
こうした反応が大半でした。
有給休暇は、雇用形態に関係なく付与される権利です。 コンビニバイトでも、コールセンターのバイトでも、飲食店のバイトでも同じです。
「週○日勤務」「6ヶ月継続」で何日もらえるのか
有給休暇が付与される条件は以下の2つです。
有給付与の条件
- 雇い入れから6ヶ月以上継続して勤務している
- その期間の全労働日の8割以上出勤している
この2つの条件を満たせば、週の勤務日数に応じて有給が付与されます。
簡単な例
- 週3日勤務で6ヶ月継続 → 5日の有給が付与される
- 週5日勤務で6ヶ月継続 → 10日の有給が付与される
詳しい日数については、次のセクションで表を使って説明します。
8割出勤の計算
「8割出勤」とは、シフトに入った日数のうち、実際に出勤した日数が8割以上という意味です。
例:6ヶ月で100日のシフト予定があった場合
- 80日以上出勤していればOK
- 20日以内の欠勤なら問題なし
体調不良での欠勤や、やむを得ない事情での休みも含まれます。 よほど頻繁に休まない限り、8割はクリアできるはずです。
店長時代の実例:有給を知ってるバイトは意外と少ない
私が店長として勤務していた期間、常に15〜20人程度のアルバイトスタッフを抱えていました。
そのうち、有給休暇の存在を知っていたのは、多くても2〜3人程度。
よくあったパターン
パターン1:知らずに辞める
- 1年以上働いたスタッフが退職
- 有給が20日近く残っているのに使わずに辞める
- 後から「有給があったんですね…」と後悔
パターン2:店長に言い出せない
- 有給があることは知っている
- でも「人手不足だから言いづらい」と遠慮
- 結局使わないまま消滅
パターン3:申請したら断られた
- 有給を申請したら「その日は無理」と言われる
- 法的には問題のある対応だが、泣き寝入り
こうした状況を見てきて、私は「スタッフに有給の存在をもっと積極的に伝えるべきだ」と痛感しました。
それ以降、新人研修の際には必ず有給休暇について説明し、6ヶ月経過したスタッフには「有給が付与されましたよ」と個別に伝えるようにしていました。
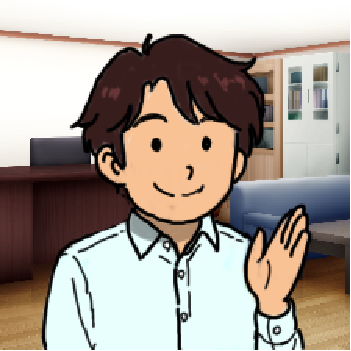
有給はいつから・何日もらえる?【付与条件と日数表】

6ヶ月勤務+8割出勤で付与
有給休暇は、以下の条件を満たした時点で付与されます。
付与のタイミング
- 入社日から6ヶ月後
- その後は1年ごとに追加付与
例:2024年4月1日入社の場合
- 2024年10月1日:初回付与(6ヶ月後)
- 2025年10月1日:2回目付与(1年6ヶ月後)
- 2026年10月1日:3回目付与(2年6ヶ月後)
週の勤務日数・勤続年数ごとの表を簡潔に掲載
有給の付与日数は、週の勤務日数と勤続年数によって決まります。
週5日勤務の場合(フルタイム相当)
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
週4日勤務の場合
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 7日 |
| 1年6ヶ月 | 8日 |
| 2年6ヶ月 | 9日 |
| 3年6ヶ月 | 10日 |
| 4年6ヶ月 | 12日 |
| 5年6ヶ月 | 13日 |
| 6年6ヶ月以上 | 15日 |
週3日勤務の場合
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 5日 |
| 1年6ヶ月 | 6日 |
| 2年6ヶ月 | 6日 |
| 3年6ヶ月 | 8日 |
| 4年6ヶ月 | 9日 |
| 5年6ヶ月 | 10日 |
| 6年6ヶ月以上 | 11日 |
週2日勤務の場合
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 3日 |
| 1年6ヶ月 | 4日 |
| 2年6ヶ月 | 4日 |
| 3年6ヶ月 | 5日 |
| 4年6ヶ月 | 6日 |
| 5年6ヶ月 | 6日 |
| 6年6ヶ月以上 | 7日 |
週1日勤務の場合
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 1日 |
| 1年6ヶ月 | 2日 |
| 2年6ヶ月 | 2日 |
| 3年6ヶ月 | 2日 |
| 4年6ヶ月 | 3日 |
| 5年6ヶ月 | 3日 |
| 6年6ヶ月以上 | 3日 |
週1日でも、継続して働いていれば有給は付与されます。 これは法律で定められたルールなので、店舗側が「うちは出さない」ということはできません。
勤務シフトがバラつく人の扱いも補足
「週によってシフトがバラバラなんだけど、私の場合は何日もらえるの?」
こうした質問もよく受けました。
シフトが不規則な場合は、過去の実績から週平均を算出して判断します。
計算方法
- 過去6ヶ月の総勤務日数を数える
- それを週換算する(6ヶ月≒26週)
- 週平均の勤務日数を出す
例:6ヶ月で78日勤務した場合
- 78日 ÷ 26週 = 週平均3日
- 週3日勤務の表を適用 → 5日付与
私が店長時代、シフトが不規則なスタッフについては、この計算をして本人に伝えていました。
「あなたの場合は週平均○日なので、有給は○日ですよ」と明確に示すことで、納得してもらえました。
分からない場合は、店長や本部に「私の有給は何日ですか?」と聞いてみましょう。 店舗側には計算する義務があります。
実際、コンビニで有給は取れるの?店長の本音

小規模店舗では「人手がいない」が最大の壁
ここからは、現場のリアルな話をします。
法律上、有給休暇はすべての労働者に認められた権利です。 しかし、コンビニの現場では「取りづらい空気」があるのも事実です。
有給が取りづらい理由
理由1:慢性的な人手不足
- コンビニは常にギリギリの人数で運営している
- 一人休むと、他のスタッフに負担がかかる
- 店長が「できれば休まないでほしい」と思ってしまう
理由2:シフト調整の難しさ
- 急な有給申請だと、代わりのスタッフが見つからない
- 特に夜勤は人手が限られている
- 店長が自ら穴埋めに入ることになる
理由3:有給を知らない・理解していない店長もいる
- アルバイトにも有給があることを知らない店長も存在する
- 「バイトに有給なんてない」と誤解している
- 法律を正しく理解していない
私が店長時代に心がけていたのは、「有給は労働者の当然の権利」という認識を持つことでした。
ただし、それでも「このタイミングで休まれると困る…」と感じることはありました。
だからこそ、申請のタイミングと伝え方が重要になります。
申請のタイミングと伝え方(例:「〇日に休みを有給でお願いしたいです」)
有給を取得する際、法律上は「いつでも自由に取れる」のが原則です。
しかし、現場の実態として、スムーズに取得するには工夫が必要です。
おすすめの申請方法
ステップ1:できるだけ早めに伝える
- 最低でも1週間前、できれば2週間前
- 繁忙期を避ける(年末年始、お盆、ゴールデンウィークなど)
- シフトが決まる前に伝える
ステップ2:具体的に伝える
- 「○月○日に休みを有給でお願いしたいです」
- 曖昧な言い方ではなく、日付を明確に
- 「有給で」と明言することが大切
ステップ3:理由を簡単に添える
- 法律上、理由を言う義務はない
- ただし、現場の人間関係として、簡単に伝えると印象が良い
- 「試験があるので」「旅行に行くので」など
実際の会話例
NG な言い方
- 「来週休みたいんですけど…」(曖昧、有給とは言っていない)
- 「明日急に休みます」(急すぎる)
- 「有給使うんで休みます」(一方的で配慮がない印象)
OK な言い方
- 「来月15日に用事があるので、有給をいただきたいのですが」
- 「試験が○日にあるので、有給で休ませていただけますか」
- 「以前からお話ししていた旅行の件ですが、○日〜○日を有給でお願いできますか」
私が店長時代、こうした丁寧な申請をしてくれるスタッフには、できる限り希望を通すようにしていました。
店長が嬉しい有給申請の仕方(代わりを提案する・早めに言う)
店長の立場から言うと、以下のような申請は非常に助かります。
店長が嬉しい申請のポイント
ポイント1:早めに伝える
- シフト作成前に伝えてもらえると調整しやすい
- 1〜2週間前なら、代わりのスタッフを探す時間がある
ポイント2:代わりを提案する
- 「○○さんがその日入れると言っていたので、お願いできませんか?」
- 自分で代わりを見つけてくれると、店長の負担が減る
- ただし、これは必須ではない
ポイント3:繁忙期を避ける
- 年末年始、お盆、連休など、明らかに忙しい時期は避ける
- どうしてもの場合は、より早めに相談
ポイント4:複数日連続の場合は相談
- 3日以上連続で休む場合は、事前に相談
- 「この期間休むのは難しいですか?」と聞いてもらえると調整しやすい
私が店長時代、こうした配慮をしてくれるスタッフには、できる限り希望を叶えたいと思っていました。
逆に、前日や当日に「明日有給で休みます」と言われると、正直困りました。
法律上は認められていても、現場としては対応が難しいのです。
有給は労働者の権利ですが、職場の人間関係を良好に保つためにも、できる範囲での配慮は大切だと思います。
有給を断られたらどうすればいい?【法的ルール】

原則、店長は「理由なく拒否できない」
ここで重要な法律知識をお伝えします。
有給休暇は、労働者が請求した時季に与えなければならない(労働基準法第39条)
つまり、原則として店長や会社は、有給の取得を拒否できません。
「その日は忙しいから無理」
「人がいないから別の日にして」
こうした理由だけでは、法律上は拒否できないのです。
ただし、例外があります。それが「時季変更権」です。
時季変更権の説明(「繁忙期にずらす」場合の対応)
時季変更権とは、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者(店長や会社)が有給の時季を変更できる権利です。
時季変更権が認められるケース
条件1:事業の正常な運営に著しい支障がある
- その日に休まれると、営業ができなくなる
- 代わりのスタッフを見つけることが不可能
- 明らかに繁忙期で、最低限の人員も確保できない
条件2:代替要員の確保に努力したが無理だった
- 他のスタッフに声をかけた
- シフト調整を試みた
- それでも人員が確保できなかった
条件3:別の日を提案する
- 「この日は無理だが、○日なら大丈夫」と代替案を示す
私が店長時代、時季変更権を使ったことは数回程度です。
具体的には、年末年始の最繁忙期に、複数のスタッフが同じ日に有給を申請した場合などです。
その際も、「○日は他のスタッフも休みで、店を開けられなくなってしまうので、前日や翌日にずらせませんか?」と丁寧にお願いしました。
時季変更権は、単に「忙しいから」「人手が足りないから」という理由だけでは使えません。
「事業の正常な運営に著しい支障」という、かなり厳しい条件が必要です。
もし店長が「その日は無理」と言ってきた場合は、以下を確認しましょう。
確認すべきこと
- なぜその日は無理なのか、具体的な理由
- 代わりのスタッフを探す努力をしたか
- いつなら取得できるのか、代替日の提案
理由が曖昧だったり、代替日の提案がない場合は、法的に問題がある可能性があります。
それでも取れない場合の相談先(労基署など)
有給の申請を断られ、時季変更権も適切に使われていない場合、どうすればいいのでしょうか。
相談の手順
ステップ1:まず本部に相談
- コンビニチェーンの本部には人事部や労務担当がいる
- 店長と直接話しづらい場合は、本部に相談
- 「有給を取得したいが、店長に断られている」と伝える
ステップ2:労働基準監督署に相談
- 本部でも解決しない場合は、労基署へ
- 最寄りの労働基準監督署に電話または訪問
- 無料で相談できる
ステップ3:証拠を残す
- 有給申請の記録(メール、LINE、メモなど)
- 断られた際の会話内容
- シフト表や勤怠記録
私が店長時代、本部から「有給の取得を妨げないように」という指導を受けたこともありました。
大手チェーンほど、法令遵守には厳しいです。
もし不当に有給を断られている場合は、泣き寝入りせず、適切な機関に相談することをおすすめします。
残業代と同じように、有給も労働者の正当な権利です。
有給を上手に使うコツ【おすすめの使い方3選】

連休につなげる
有給を効果的に使う方法の一つが、既存の休みと組み合わせて連休にすることです。
連休の作り方
パターン1:土日と組み合わせる
- 金曜に有給 → 土日と合わせて3連休
- 月曜に有給 → 土日と合わせて3連休
パターン2:祝日と組み合わせる
- 祝日の前後に有給 → 3〜4連休
パターン3:複数日の有給を使う
- 月〜水に有給 → 土日と合わせて5連休
私が店長時代、こうした使い方をするスタッフは多くいました。
特に学生は、テスト期間や長期休暇の前後に有給を使って、連休を作っていました。
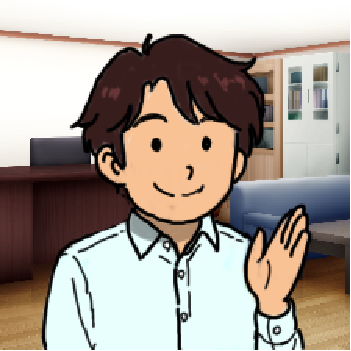
試験・旅行・冠婚葬祭など目的を明確に
有給は、どんな理由で使っても構いません。
法律上、理由を言う義務はありませんが、現場の関係性として、簡単に伝えると印象が良いです。
よくある使用目的
- 大学の試験期間
- 資格試験の受験
- 家族旅行
- 友人の結婚式
- 実家への帰省
- 体調不良での療養
- 免許の更新
- 引っ越し
私が店長時代、「試験があるので」「結婚式に出席するので」と言われた場合は、快く了承していました。
正当な理由があれば、店長も納得しやすいです。
使い方のコツ
- 理由は簡潔に(詳しく説明する必要はない)
- 嘘をつく必要はない(「私用」でもOK)
- 計画的に使う(無駄に消化するのではなく、本当に必要な時に)
有給は、あなたの生活を豊かにするための制度です。 遠慮せず、必要な時にしっかり使いましょう。
「退職前の有給消化」も合法的に可能
有給休暇には、退職時にまとめて使える「有給消化」があります。
退職時の有給消化
退職を決めた際、残っている有給をすべて使ってから辞めることができます。
例:3月31日付けで退職、有給が10日残っている場合
- 3月20日まで通常勤務
- 3月21日〜31日を有給消化
- 実質的な最終出勤日は3月20日
これは完全に合法です。
私が店長時代、退職するスタッフには「有給は何日残っていますか?使いますか?」と必ず確認していました。
引き継ぎとのバランス
ただし、退職時の有給消化には配慮も必要です。
配慮すべきポイント
- 引き継ぎ期間を確保する
- 退職の1〜2ヶ月前には伝える
- 有給消化のスケジュールを事前に相談
「明日から有給消化して、そのまま辞めます」というのは、法律上は可能ですが、現場には大きな負担がかかります。
円満に退職するためには、ある程度の配慮が必要だと思います。
夜勤など特殊なシフトの場合は、特に引き継ぎが重要です。
まとめ:知ってるだけで得をする”有給の権利”

有給を理解してるだけで損しない
この記事で最もお伝えしたかったのは、「有給休暇はアルバイトにも認められた権利」ということです。
有給休暇のポイントまとめ
- 6ヶ月継続+8割出勤で必ず付与される
- 週1日勤務でも有給はもらえる
- 付与日数は週の勤務日数と勤続年数で決まる
- 原則として、店長は取得を拒否できない
- 退職時にまとめて使うこともできる
私が店長として20年以上働いてきて痛感したのは、「知らないと損をする」ということです。
有給の存在を知らずに辞めていったスタッフが何人もいました。 非常にもったいないことです。
給料日や深夜手当、休憩時間と同じように、有給休暇も自分の権利として理解しておきましょう。
現場も「有給を理解してる人」のほうが信頼されやすい
有給を正しく理解し、適切に使える人は、店長からも信頼されます。
信頼されるスタッフの特徴
- 権利と義務のバランスを理解している
- 早めに申請し、配慮ある対応をする
- 職場の状況も考えながら、自分の権利も主張できる
私が店長時代、有給を上手に使うスタッフは、総じて仕事もしっかりしている人が多かったです。
自分の権利を理解し、それを適切に行使できる人は、仕事に対しても責任感があります。
逆に、「有給なんて取ったら悪い」と遠慮しすぎる人は、他の面でも自分を犠牲にしすぎて、結果的に疲弊してしまうことがありました。
有給は、あなたの心身をリフレッシュさせ、より良い状態で働くための制度です。 遠慮せず、計画的に使いましょう。
最後に:法律を味方につけて、働きやすい環境を
有給休暇は、労働基準法で定められた、すべての労働者の権利です。
コンビニバイトであっても、週1日の勤務であっても、条件を満たせば必ず付与されます。
もし不当に有給を断られたり、有給の存在を教えてもらえない場合は、それは法律違反です。
遠慮せず、本部や労働基準監督署に相談しましょう。
私が店長として働いてきた中で学んだのは、「法律を正しく理解している店舗ほど、スタッフの定着率が高い」ということです。
スタッフの権利を尊重し、働きやすい環境を作ることが、結果的に店舗の利益にもつながります。
あなたも、自分の権利を正しく理解して、損をしない働き方をしてください。
コンビニバイトで充実した経験を積むために、有給休暇という制度を上手に活用しましょう。
何かご質問があれば、いつでも「コンビニぐらし」でお待ちしています!
よくある質問(FAQ)
Q1. コンビニバイトでも有給は必ずもらえますか?
A. はい、条件を満たせば必ず付与されます。
6ヶ月継続勤務+8割以上出勤という条件を満たせば、雇用形態に関係なく有給休暇は付与されます。
「バイトだから」「パートだから」という理由で付与されないことはありません。
もし付与されていない場合は、店長や本部に確認しましょう。
Q2. 有給を使うと給料は減りますか?
A. 減りません。出勤扱いで通常どおり支給されます。
有給休暇は「休んでいても給料が支払われる」制度です。
通常のシフトと同じように、その日の分の給料が支払われます。
例:時給1,000円、8時間勤務の日を有給で休んだ場合
- 給料は8,000円支払われる(欠勤ではないため)
給料日に、通常通り振り込まれます。
Q3. 有給を申請したのにシフトに入れられました…?
A. 原則NGです。時季変更権を使う場合でも事前に説明が必要です。
有給を申請したのに、勝手にシフトに入れられている場合は、以下を確認しましょう。
確認すべきこと
- 店長に「有給を申請したはずですが」と伝える
- シフトのミスなのか、時季変更権を使ったのか確認
- 時季変更権を使う場合は、その理由と代替日を聞く
単なるミスであれば、すぐに修正してもらいましょう。
もし「やっぱり出勤してほしい」と言われた場合は、理由を明確に聞き、納得できなければ断ることもできます。
Q4. 有給の理由は言わなきゃダメですか?
A. 法律上、理由を言う義務はありません。
有給休暇は、理由を問わず取得できる権利です。
「私用のため」とだけ伝えても、法的には問題ありません。
ただし、職場の人間関係を良好に保つために、簡単に理由を伝える方が印象は良いでしょう。
「旅行に行くので」「試験があるので」など、一言添えるだけでも十分です。
Q5. 有給が残っているまま辞めたらどうなりますか?
A. 原則として消滅します。退職前に使い切るのがおすすめです。
有給休暇は、退職すると消滅します。
「退職後にお金でもらう」こともできません(法的には可能ですが、会社側の義務ではない)。
そのため、退職を決めたら、残っている有給をすべて使ってから辞めるのが賢い方法です。
退職日から逆算して、有給消化期間を設定しましょう。
例:3月31日退職、有給10日残っている場合
- 3月18日まで通常勤務
- 3月19日〜31日(平日のみ10日)を有給消化
- 実質的な最終出勤日は3月18日
ただし、引き継ぎ期間も考慮して、円満に退職できるよう配慮しましょう。
Q6. パートから正社員になったら有給はどうなりますか?
A. 継続して勤務していれば、通算されます。
同じ会社で、パートから正社員に雇用形態が変わった場合、勤続年数は通算されます。
例:パートで1年働いた後、正社員になった場合
- 正社員になってから6ヶ月後ではなく、既に1年6ヶ月の扱い
- 有給日数も勤続年数に応じて付与される
ただし、一度退職して、再度入社した場合は、勤続年数はリセットされます。
関連記事
- コンビニバイトの給料日はいつ?
- コンビニ夜勤の時給はいくら?深夜手当の仕組みとメリット・デメリット
- コンビニバイトの休憩時間はどれくらい?
- コンビニバイトに残業ってある?残業代の仕組みと注意点
- コンビニ夜勤あるある8選と初心者が注意すべきポイント
- コンビニバイトのシフトの決め方











