こんにちは!「コンビニぐらし」の木内澄也です。
コンビニ業界に20年以上従事し、店長として多くのスタッフの悩みに向き合ってきました。
「仕事自体は慣れてきたけど、人間関係がつらい…」
コンビニバイトでよく聞く悩みのひとつです。
気の強い先輩、無愛想な社員、シフトで顔を合わせるたびに気を使う同僚…。
小さなストレスが積み重なって、「もう辞めたい」と感じる人も多いでしょう。
私が店長時代、退職理由を聞くと「仕事内容は好きだったんですが、人間関係が…」という声が本当に多かったです。
実際、コンビニの人間関係は独特の難しさがあります。
狭い空間で、年齢も性格もバラバラな人たちと長時間過ごす。 これは、誰にとってもストレスになりうる環境です。
でも、だからといって「我慢するしかない」わけではありません。
この記事では、コンビニ店長経験から、これまで多くのスタッフを見てきた中で感じた「人間関係がうまくいく人の特徴」と「距離の取り方のコツ」をお話しします。
- なぜコンビニの人間関係はしんどいのか
- うまくやっている人の共通点
- 苦手な人との距離の取り方
- 我慢できないときの最終手段
シフトカットやミス対応と同じように、人間関係も「正しい対処法」を知っていれば、ストレスを減らせます。
少しでも気持ちを軽くして、無理せず働けるヒントを持ち帰ってください。
コンビニバイトの人間関係がしんどいと感じる理由

狭い職場だからこそ人間関係が密になりやすい
コンビニは、店舗面積が50〜150平米程度の小さな空間です。
その中で、レジ、バックヤード、トイレなど、限られたスペースを共有します。
コンビニ特有の環境
- 店舗が狭く、常に誰かが視界に入る
- 休憩室も狭く、一人になれる時間が少ない
- レジとバックヤードを行き来するため、嫌でも顔を合わせる
- シフトが固定されていると、同じメンバーと長時間過ごす
私が店長時代、スタッフから「もっと広い職場で働きたい」という声をよく聞きました。
確かに、大型スーパーや工場などと比べると、コンビニは圧倒的に狭いです。
距離感の難しさ
狭い空間では、距離感を保つのが難しくなります。
- 苦手な人がいても、避けられない
- 一度気まずくなると、その空気がずっと続く
- プライベートな話を聞かれやすい
- 休憩中も気を使う
私の店舗でも、狭いバックヤードで二人きりになったとき、気まずい沈黙が流れる…というシーンを何度も見てきました。
広い職場なら、物理的に距離を取れます。 でもコンビニでは、それが難しいのです。
年齢差・性格差が大きい環境
コンビニには、実に多様な人が働いています。
スタッフの年齢層
- 高校生(16歳〜)
- 大学生(18〜22歳)
- フリーター(20〜40代)
- 主婦・主夫(30〜60代)
- シニア(60代以上)
私の店舗では、最年少が16歳の高校生、最年長が68歳のシニアスタッフでした。
50歳以上の年齢差があるメンバーが、同じ職場で働いているのです。
世代間のギャップ
世代が違うと、価値観や働き方も異なります。
よくあるギャップ
- 若い世代:効率重視、マニュアル通りにやりたい
- 年配世代:経験重視、「昔はこうだった」という話が多い
- 学生:シフトの融通を求める
- 主婦層:家庭優先で急な休みが多い
こうした違いが、ときに衝突を生みます。
私が店長時代、よく仲裁に入ったのが、「若いスタッフが年配スタッフのやり方に不満を持つ」というパターンでした。
「あの人、全然マニュアル通りにやらないんです」
「私のやり方を否定された」
どちらも間違っていないのですが、価値観が違うために摩擦が生まれるのです。
性格の違いも大きい
年齢だけでなく、性格の違いも人間関係に影響します。
性格の違い
- 社交的な人 vs 内向的な人
- 几帳面な人 vs おおらかな人
- おしゃべりな人 vs 静かな人
- リーダータイプ vs フォロワータイプ
こうした多様性は、本来は職場の強みです。 でも、お互いを理解し合えないと、ストレスの原因になります。
「あの人とは合わない」が仕事に影響しやすい
コンビニの特徴として、少人数体制での勤務があります。
少人数体制の影響
体制の特徴
- 日中は2〜3人体制
- 夜勤は1人体制(ワンオペ)
- ピーク時でも4〜5人程度
つまり、苦手な人と二人きりになる確率が非常に高いのです。
私が店長時代、こんな相談をよく受けました。
「あの人とシフトが一緒だと思うと、出勤が憂鬱です」
気持ちはよくわかります。
大規模な職場なら、苦手な人がいても別のチームで働けます。 でもコンビニでは、二人きり、または少人数で働かざるを得ません。
仕事への影響
人間関係の悪化は、仕事にも影響します。
影響の例
- コミュニケーションが減り、ミスが増える
- 引き継ぎが不十分になる
- チームワークが崩れる
- 職場の雰囲気が悪くなる
私の店舗でも、スタッフ同士が険悪になった結果、引き継ぎがおろそかになり、お客様対応でトラブルが起きたことがありました。
人間関係は、店舗運営にも大きく影響するのです。
店長が見てきた「うまくやる人」の特徴

「誰とでも挨拶を欠かさない」
私が店長として20年以上働いてきた中で、人間関係がうまい人には共通点がありました。
その第一が、「挨拶」です。
挨拶の重要性
- 最低限のコミュニケーションになる
- 「無視された」という感情を防げる
- 「普通に接してくれる人」という印象を与える
- 自分からの歩み寄りの姿勢を示せる
私の店舗で、全員から好かれていたスタッフがいました。
その人は、特別に社交的なわけでも、おしゃべりなわけでもありませんでした。
でも、必ず全員に挨拶をしていました。
「おはようございます」 「お疲れ様です」 「ありがとうございます」
この3つを、誰に対しても欠かさない。
たったそれだけで、「感じのいい人」という評価を得ていました。
挨拶のコツ
- 相手が誰であっても、必ず挨拶する
- 笑顔は無理でも、せめて声は明るく
- 目を見て挨拶する(一瞬でいい)
- 「おはようございます」「お疲れ様でした」は最低限
苦手な人にも挨拶する。 これが、実は人間関係を円滑にする最も簡単な方法です。
私が店長時代、新人には必ず「挨拶だけは絶対に欠かさないように」と伝えていました。
「ほどよく聞き役になれる」
人間関係がうまい人のもう一つの特徴が、「聞き役になれる」ことです。
ただし、「何でも聞く」のではなく、「ほどよく聞く」のがポイントです。
聞き役のメリット
- 相手が話しやすくなる
- 「この人は信頼できる」と思われる
- 自分が余計なことを言わずに済む
- トラブルに巻き込まれにくい
私の店舗で、ベテランの主婦スタッフがいました。
その人は、ほとんど自分のことを話しませんでしたが、他のスタッフの話をよく聞いていました。
「そうなんだ、大変だったね」
「へぇ、そういうことがあったんだ」
こうした相槌を打ちながら、聞き役に徹していました。
結果、多くのスタッフから信頼されていました。
聞き役のコツ
- 相手の話を遮らない
- 共感の相槌を打つ(「そうなんだ」「大変だね」)
- アドバイスは求められたときだけ
- プライベートに踏み込みすぎない
ただし、聞きすぎも注意です。
聞きすぎのデメリット
- 愚痴のはけ口にされる
- 悪口に巻き込まれる
- 時間を取られすぎる
- 自分がストレスを溜める
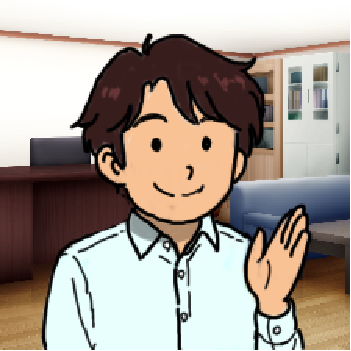
「悪口や陰口に加わらない」
これは、私が店長として最も重視していたポイントです。
悪口・陰口の危険性
- 必ず本人の耳に入る
- 信頼を失う
- トラブルの火種になる
- 自分も悪口を言われる対象になる
コンビニは狭い職場です。
「ここだけの話」は、ほぼ確実に広まります。
私が店長時代、スタッフ同士の陰口が原因で、職場の雰囲気が最悪になったことがありました。
Aさんが、Bさんの悪口をCさんに言う。 CさんがDさんに話す。 Dさんが、たまたまBさんの友達だった。 Bさんに伝わる。
こうして、職場が二つのグループに分断されました。
人間関係がうまい人の対応
- 悪口が始まったら、話題を変える
- 「私はよくわからないので」と距離を取る
- 相槌を打つだけで、同調しない
- 「でも、いい面もあるよね」とフォローする
私の店舗で、絶対に悪口に加わらないスタッフがいました。
誰かが悪口を言い始めても、「でも、〇〇さんって仕事は丁寧だよね」とフォローしていました。
最初は「優等生ぶってる」と思われたかもしれません。
でも、結果的に誰からも信頼されるスタッフになりました。
店長からのアドバイス
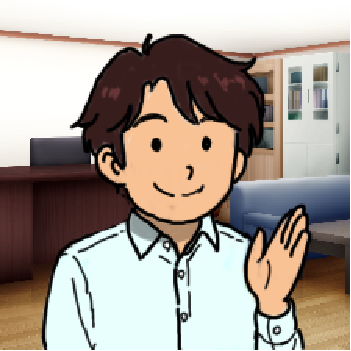
悪口に加わらないことは、自分を守ることにもなります。
今は悪口を言う側でも、いつか自分が言われる側になるかもしれません。
「悪口を言わない人」という評価を得ることが、長期的には最も得策です。
ミス対応でも触れていますが、誠実な態度が信頼を作ります。
距離を取りたいときの上手な立ち回り方

最低限の会話で”業務だけ”をこなす
「どうしてもこの人とは合わない」
そう感じることは、誰にでもあります。
無理に仲良くする必要はありません。
業務に徹する方法
- 挨拶は必ずする(これは最低限のマナー)
- 業務連絡は明確に、丁寧に行う
- プライベートな話は避ける
- 休憩時間は別々に取る
- 必要以上に話しかけない
私が店長時代、明らかに相性が悪い二人がいました。
でも、二人とも「業務に徹する」姿勢を貫いていました。
プライベートな話は一切しない。 でも、引き継ぎや報告は丁寧に行う。
結果として、お互いに不快にならず、仕事も円滑に進みました。
会話の例
業務的な会話
- 「レジの釣り銭が少なくなっているので、補充お願いします」
- 「〇〇の発注、今日中にお願いできますか」
- 「お疲れ様でした」
プライベートな会話(避ける)
- 「休みの日は何してるんですか?」
- 「彼氏(彼女)いるんですか?」
- 「どこに住んでるんですか?」
業務に必要なことだけ話す。 それ以上は踏み込まない。
これが、苦手な人との最も無難な距離感です。
シフトをずらしてストレスを減らす
どうしても一緒に働くのがストレスな場合、シフトをずらすことも有効です。
シフトをずらす方法
方法1:希望シフトを調整する
- 相手がよく入る曜日を避ける
- 時間帯をずらす(早番↔遅番)
- シフト希望を早めに出す
方法2:店長に相談する
- 「できれば〇曜日は避けたいです」と伝える
- 理由は「他の予定がある」など、角が立たない言い方
- 露骨に「あの人と一緒は嫌です」とは言わない
私が店長時代、こうした相談は意外と多かったです。
「できれば、〇〇さんとシフトが重ならないようにしていただけませんか?」
こう言われたとき、理由を詳しく聞くことはしませんでした。
察して、できる範囲で調整していました。
注意点
ただし、完全に避けるのは難しいこともあります。
難しいケース
- 人数が少ない店舗
- 相手がベテランで固定シフトが決まっている
- 自分が新人で、シフトの融通が利きにくい
その場合は、せめて「二人きりになる時間を減らす」ことを目指しましょう。
店長に”やんわり相談”しておくのもOK
苦手な人がいることを、店長に伝えておくのも一つの方法です。
ただし、伝え方には注意が必要です。
伝え方のコツ
NG な言い方
- 「あの人が嫌いなので、一緒に働きたくないです」(直接的すぎる)
- 「あの人のせいで辞めたいです」(感情的)
- 「あの人を辞めさせてください」(無理な要求)
OK な言い方
- 「少し働きづらさを感じているので、相談させてください」
- 「〇〇さんとはコミュニケーションの取り方が難しくて…」
- 「できれば、シフトを少しずらしていただけると助かります」
私が店長時代、こうした相談を受けたとき、まず「具体的に何があったか」を聞いていました。
店長が確認すること
- パワハラやいじめに該当するか
- 業務に支障が出ているか
- 改善の余地があるか
- シフト調整で解決できるか
もしパワハラやいじめがある場合は、店長として対応する義務があります。
そうでない場合でも、シフト調整など、できる範囲で配慮していました。
相談のタイミング
- ストレスが限界に達する前
- 具体的な問題が起きたとき
- 業務に影響が出始めたとき
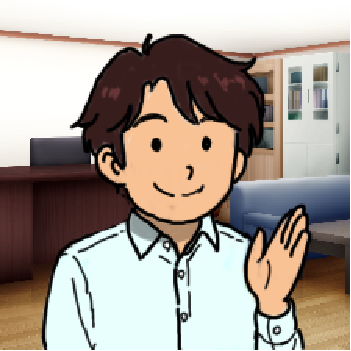
人間関係が合わないときの最終手段

店長・オーナーに相談して異動を提案
シフト調整や距離の取り方でも改善しない場合、店舗異動という選択肢があります。
店舗異動のメリット
- 人間関係をリセットできる
- 同じチェーンなら、仕事内容は変わらない
- 時給や待遇も基本的に同じ
- 辞めずに続けられる
私が店長時代、実際に店舗異動を提案したことが何度かあります。
実例:異動で改善したケース
あるスタッフが、特定の先輩スタッフとどうしても合わず、出勤が憂鬱になっていました。
本人から「辞めたい」と相談を受けたとき、私は「辞める前に、別の店舗で働いてみない?」と提案しました。
エリアマネージャーに相談し、車で10分ほどの別店舗に異動。
異動後、本人から「今の店舗はすごく働きやすいです」と連絡をもらいました。
結局、その店舗で2年以上働き続けました。
異動の相談方法
- 店長に「別の店舗で働くことは可能ですか?」と聞く
- 理由は「通勤時間」「環境を変えたい」など、角が立たない言い方
- 店長→オーナー→本部と相談が進む
- 受け入れ先の店舗があれば、異動可能
ただし、すべてのチェーンで異動ができるわけではありません。
異動が難しいケース
- フランチャイズ店(オーナーが違う)
- 近隣に店舗がない
- 受け入れ先の店舗が人員充足している
可能性があるなら、一度相談してみる価値はあります。
辞める前に「別の店舗で続ける」という選択肢も
「もう辞めよう」と決める前に、別の店舗も検討してみてください。
別の店舗のメリット
- 今の経験を活かせる
- 一から仕事を覚え直す必要がない
- 収入が途切れない
- 履歴書に「短期離職」が増えない
私が店長時代、「辞めます」と言ってきたスタッフに、必ずこう聞いていました。
「仕事内容が嫌なの?それとも人間関係?」
ほとんどの場合、答えは「人間関係」でした。
そういうときは、「別の店舗なら続けられるかもしれないよ」と提案していました。
他のチェーンも選択肢
同じチェーンでの異動が難しい場合、別のチェーンのコンビニに応募するのも手です。
別チェーンのメリット
- 経験者として優遇される
- 時給交渉がしやすい
- 環境を完全にリセットできる
コンビニの経験は、どのチェーンでも活かせます。
「前のコンビニで1年働いていました」と言えば、即戦力として採用されやすいです。
人間関係が原因で辞めるなら、「コンビニ自体を辞める」のではなく、「その店舗を辞める」と考えてみてください。
無理せず離れる勇気も大事
ただし、それでも無理なら、離れる勇気も必要です。
辞めるべきサイン
こんなときは辞めることも検討
- 体調を崩すほどストレスが大きい
- 出勤前に吐き気や頭痛がする
- 夜眠れない、食欲がない
- パワハラやいじめがある
- 店長に相談しても改善されない
私が店長として最も後悔しているのは、あるスタッフが体調を崩すまで気づけなかったことです。
そのスタッフは、特定の先輩からのいじめに耐えていました。
私が気づいたときには、すでに心身ともに限界でした。
「もっと早く相談してくれれば…」と思いましたが、本人は「迷惑をかけたくない」と我慢していたのです。
あなたの健康が最優先
仕事よりも、お金よりも、あなたの健康が最優先です。
無理して続けて体を壊すくらいなら、離れる勇気を持ってください。
有給休暇が残っているなら、しっかり消化してから辞めましょう。
次の職場は、必ず見つかります。
コンビニの経験は、どこでも評価されます。
自分を大切にしてください。
まとめ|自分の心を守ることを最優先に

人間関係は「完璧」でなくていい
この記事で最もお伝えしたかったのは、「人間関係は完璧でなくていい」ということです。
無理に仲良くする必要はない
大切なこと
- 全員と仲良くする必要はない
- 最低限の挨拶と業務連絡ができればOK
- 苦手な人がいるのは普通のこと
- 距離を取ることも、立派な対処法
私が店長として20年以上働いてきて、「全員と仲が良い職場」なんて見たことがありません。
どの職場にも、合う人・合わない人がいます。
それは当たり前のことです。
うまくやるコツは「挨拶」「聞き役」「悪口に加わらない」
人間関係がうまい人の共通点をまとめます。
うまくやる人の特徴
- 誰に対しても挨拶を欠かさない
- ほどよく聞き役になれる
- 悪口や陰口に加わらない
- プライベートに深入りしすぎない
- 業務に必要なコミュニケーションは丁寧に行う
これらは、特別な才能ではありません。
誰でも、今日から実践できることです。
距離を取る方法も「戦略」の一つ
苦手な人がいるとき、無理に仲良くしようとする必要はありません。
距離の取り方まとめ
- 業務に徹する(プライベートな話は避ける)
- シフトをずらす
- 店長にやんわり相談する
- 最低限の挨拶と連絡は忘れずに
距離を取ることは、逃げではありません。
自分を守るための、立派な戦略です。
最終手段は「異動」「転職」「退職」
それでも無理なら、環境を変えることも選択肢です。
最終手段まとめ
- 店舗異動を相談する
- 別のチェーンのコンビニに応募する
- コンビニ以外の仕事を探す
- 体調を優先して退職する
シフトカットやミス対応と同じように、人間関係も「我慢するしかない」ものではありません。
対処法があります。
あなたの心を守ることが最優先
最後に、私から一番伝えたいこと。
あなたの心と体が、何よりも大切です。
仕事は代わりがいます。 でも、あなたの代わりはいません。
無理をして体調を崩すくらいなら、離れてください。
次の職場は、必ず見つかります。
コンビニの経験は、どこに行っても評価されます。
人間関係で悩んでいるあなたへ。
一人で抱え込まず、信頼できる人に相談してください。
店長、家族、友人、誰でもいいです。
話すだけで、気持ちが軽くなることもあります。
この記事が、少しでもあなたの心を軽くできていたら嬉しいです。
何かご質問があれば、いつでも「コンビニぐらし」でお待ちしています!
よくある質問(FAQ)
Q1. 先輩に挨拶しても無視されます。どうすればいいですか?
A. あなたは挨拶を続けてください。相手の問題です。
挨拶を無視するのは、相手の人間性の問題であり、あなたの問題ではありません。
続けるべきこと
- あなたは挨拶を続ける
- 無視されても、気にしない
- 他のスタッフへの挨拶も必ず続ける
- 業務連絡は丁寧に行う
私が店長時代、挨拶を無視するスタッフには個別に注意していました。
「挨拶は基本的なマナーです。必ず返してください」
もし店長が何も対応しない場合は、本部に相談することも検討してください。
挨拶を無視するのは、立派なパワハラの一種です。
Q2. 悪口に加わらないと、自分が仲間外れにされそうで怖いです…
A. 一時的に距離を置かれても、長期的には信頼されます。
悪口グループに入らないことで、一時的に距離を置かれるかもしれません。
でも、長期的に見れば、悪口を言わない人の方が信頼されます。
私が店長時代、悪口グループは必ず崩壊しました。
悪口グループの末路
- 内部で対立が起きる
- 次は自分が悪口を言われる側になる
- 店長からの信頼を失う
- 最終的にバラバラになる
逆に、悪口に加わらなかったスタッフは、誰からも信頼されるベテランになっていました。
短期的には辛いかもしれませんが、長期的には正しい選択です。
Q3. シフトをずらしたいと店長に言ったら、理由を詳しく聞かれました…
A. 角が立たない理由を用意しておきましょう。
「あの人と一緒は嫌です」とは言いづらいですよね。
角が立たない理由の例
- 「大学の授業が変わったので」
- 「家族の都合で」
- 「他のバイトとの兼ね合いで」
- 「勉強時間を確保したくて」
私が店長時代、こうした相談を受けたとき、深く追及することはしませんでした。
「何か事情があるんだな」と察して、できる範囲で調整していました。
もし詳しく聞かれても、「プライベートな事情なので…」と濁すことも可能です。
Q4. 店長に人間関係の相談をしたら、逆に気まずくなりませんか?
A. 信頼できる店長なら、むしろ状況を改善してくれます。
相談することで気まずくなるのではないか…という不安、よくわかります。
でも、良い店長であれば、相談を歓迎します。
良い店長の対応
- 話を真剣に聞く
- 具体的な改善策を考える
- シフト調整などで配慮する
- 秘密を守る
私が店長時代、スタッフから人間関係の相談を受けたときは、「話してくれてありがとう」と伝えていました。
早めに相談してもらえれば、問題が大きくなる前に対処できます。
もし店長に相談して改善されない、または気まずくなった場合は、オーナーや本部に相談しましょう。
Q5. 異動したいと言ったら、辞めるしかないと言われました…
A. 本部やエリアマネージャーに直接相談してみましょう。
店長が「異動は無理」と言っても、本部に確認すれば可能なこともあります。
相談先
- エリアマネージャー
- 本部の人事部門
- スタッフ相談窓口(大手チェーンにある)
私が店長時代、本部から「別の店舗に異動させてあげてほしい」と指示を受けたことがあります。
店長レベルでは「無理」と思っても、本部が調整してくれることもあります。
諦めずに、上に相談してみてください。
Q6. 人間関係が原因で辞める場合、正直に理由を言うべきですか?
A. 角が立たない言い方をおすすめします。
退職理由を正直に言うかは、あなたの判断次第です。
ただし、「あの人が嫌だから」と言うと、最後まで気まずくなります。
角が立たない退職理由
- 「学業に専念したいので」
- 「家庭の事情で」
- 「他にやりたいことができたので」
- 「通勤時間が負担で」
私が店長時代、退職理由を深く聞くことはしませんでした。
「そうなんだね。今までありがとう」
それで終わりです。
もし本当の理由を伝えたい場合は、退職が確定してから、個別に話すのもいいでしょう。
有給休暇の消化についても、忘れずに確認してくださいね。
関連記事
- コンビニバイトでシフトを勝手に減らされた?正しい対処法
- コンビニバイトで商品を壊した・ミスした時の対処法
- コンビニバイトの有給休暇は取れる?
- コンビニバイトに残業ってある?残業代の仕組み
- コンビニ夜勤あるある8選と初心者が注意すべきポイント
- コンビニバイトのシフトの決め方












「ほどよく」がポイントです。
相手が話したいときは聞く。 でも、深入りしすぎない。
このバランスが、人間関係を円滑にします。