こんにちは!「コンビニぐらし」の木内澄也です。 コンビニ業界に20年以上従事し、店長として多くのスタッフの労働環境を管理してきました。
「コンビニバイトって休憩時間あるの?」
「忙しすぎて休憩が取れないって本当?」
「休憩中は何をしていいの?時給は出るの?」
これからコンビニバイトを始めようと考えている方から、よくこんな質問をいただきます。 実際、私が店長時代に採用面接をした際も、休憩時間について不安を持っている方が非常に多くいらっしゃいました。
休憩時間は働く上でとても大切な権利です。労働基準法で定められており、コンビニバイトでも6時間超のシフトなら休憩が必ずあります。
しかし、コンビニの現場では「忙しくて休憩が取れない」「1人勤務だから休めない」といった実態があることも事実です。
今回は、法律で定められたルールから実際の現場での休憩の取り方、そして休憩を取れないときの対処法まで、店長経験者の目線で詳しく解説していきます。
コンビニバイトの給料日と同じく、休憩時間も働く前にしっかり確認しておきたい重要な条件の一つです。
コンビニバイトの休憩時間は法律でどう決まっている?

労働基準法で定められた休憩ルール
コンビニバイトの休憩時間は、労働基準法第34条によって明確に定められています。 店長として最も気をつけていたことの一つが、この法律を守ることでした。
労働時間と休憩時間の関係
| 労働時間 | 必要な休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | 休憩なしでもOK |
| 6時間超〜8時間以下 | 最低45分 |
| 8時間超 | 最低60分(1時間) |
この表が示す通り、6時間を超える勤務の場合は必ず休憩を取る権利があるということです。 例えば、9時〜18時の8時間勤務なら、最低45分の休憩が法律で保証されています。
重要なポイントとして、休憩時間は労働時間に含まれないため時給は発生しません。 つまり、8時間勤務で1時間休憩の場合、実際に時給が発生するのは7時間分となります。
バイトにも法律は適用される?
「アルバイトだから休憩は取れないのでは?」という質問をよく受けますが、これは大きな誤解です。
労働基準法はアルバイト・パートにも完全に適用されます。
正社員だろうとアルバイトだろうと、雇用形態に関係なく同じ休憩ルールが適用されるのです。 私が店長時代、新人スタッフには必ずこの点を説明し、「遠慮せずに休憩を取ってください」と伝えていました。
.jpg)
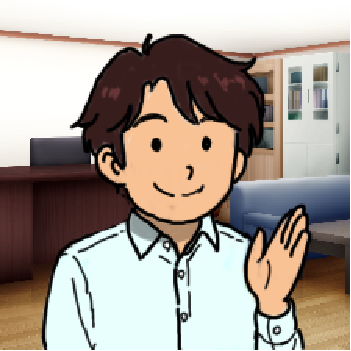
ただし、店舗によっては4〜5時間勤務でも15分程度の休憩を設けているところもありますよ。
実際のコンビニでの休憩の取り方

短時間勤務(4時間未満)の場合
4時間未満の短時間シフトでは、法律上は休憩時間が義務付けられていません。
実際の運用としては
- 3時間勤務:休憩なしが一般的
- 3.5〜4時間勤務:店舗によっては10〜15分の小休憩を設けることも
私の店舗では、3時間半以上のシフトには10分程度の小休憩を取ってもらっていました。 特に立ち仕事が続くレジ業務では、短い休憩でもスタッフの疲労回復に効果的だったからです。
4〜6時間勤務のケース(休憩なし or 15分程度)
4〜6時間の勤務は、コンビニバイトで最も一般的な時間帯です。
この時間帯の休憩パターン
- 法律上:6時間以下なので休憩義務なし
- 実際の運用:15〜30分の休憩を設ける店舗が多い
例えば、9時〜15時の6時間勤務の場合、12時頃に15分程度の休憩を取るのが一般的です。 ただし、これは法律で義務付けられているものではなく、店舗側の配慮によるものです。
私が店長時代に心がけていたのは、たとえ法律上義務がなくても、5時間以上の勤務には必ず15分以上の休憩を取ってもらうことでした。 疲労が蓄積すると接客の質が下がり、ミスも増えるからです。
6時間以上勤務のケース(30分〜1時間の休憩)
6時間を超える勤務では、法律で最低45分の休憩が義務付けられています。
実際の休憩時間の例
- 6〜8時間勤務:45分〜1時間の休憩
- 8時間超勤務:1時間の休憩
具体例を挙げると
- 9時〜17時(8時間勤務):13時〜14時の1時間休憩
- 13時〜21時(8時間勤務):16時〜17時の1時間休憩
休憩のタイミングは、シフトの組み方と密接に関係しています。 お客様が少ない時間帯や、他のスタッフと交代できるタイミングで取るのが基本です。
私の経験では、昼食時(12〜13時)と帰宅時間(17〜19時)は店舗が混雑するため、その前後に休憩を設定することが多かったです。
休憩時間は本当に取れるの?現場の実態

お客様が多いと休憩がズレることも
コンビニの休憩時間に関する最も大きな問題が、予定通りに取れないことです。
私が店長として20年以上働いてきた中で、休憩時間が予定通りに取れる日は正直なところ半分程度でした。
休憩がズレる主な理由
- 突然の来客ラッシュ
- 配送トラックの到着
- レジや機械のトラブル対応
- 他のスタッフの遅刻や欠勤
例えば、13時から休憩予定だったのに、12時50分頃から急にお客様が増えて、結局13時30分になってしまう、といったことは日常茶飯事です。
ただし、休憩時間が後ろにズレても、必ず取ることが大切です。 「忙しいから今日は休憩なし」という運用は違法ですし、スタッフの健康にも良くありません。
1人勤務シフトでは休憩が難しい場合も
深夜帯や平日昼間の1人勤務シフトでは、休憩を取ることが実質的に難しいというのが現場の実態です。
1人勤務時の問題点
- レジを離れられない
- 休憩中に来客があると対応せざるを得ない
- 実質的に「店番をしながらの休憩」になりがち
私の店舗では、1人勤務の時間帯をできるだけ短くし、6時間を超える場合は必ず2人体制にするよう調整していました。 それでも人手不足で1人勤務が避けられない場合は、オーナーや店長が休憩時間だけ店に入るなど工夫していました。
「コンビニバイトで休憩がもらえないのは違法?」という質問に対する答えは、「6時間超の勤務で休憩がないのは明確に違法」です。 1人勤務だからという理由は法律上の免除事由にはなりません。
夜勤バイトの休憩事情(仮眠できる?)
コンビニ夜勤あるあるでも触れていますが、深夜シフトの休憩は特殊な扱いになることがあります。
深夜シフトの休憩パターン
- 22時〜6時(8時間勤務):1時間の休憩が法定
- 休憩時間帯:深夜2〜3時頃が多い(最も来客が少ない時間)
- 仮眠の可否:店舗による(休憩室にソファがあれば可能な場合も)
私の店舗では、深夜スタッフの負担を考えて、休憩室にリクライニングチェアを置き、横になれる環境を整えていました。 ただし、あくまでも「休憩」であり「仮眠時間」として保証されているわけではありません。
.jpg)
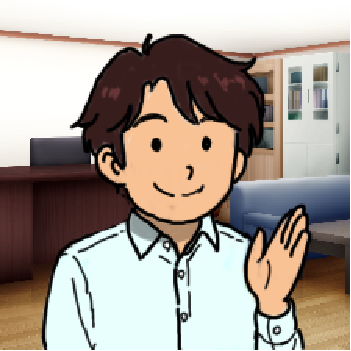
休憩を取れないときの対処法

店長に相談してシフトを調整してもらう
休憩が取れない状況が続いている場合、まずは店長やオーナーに相談することが大切です。
私が店長時代、スタッフから「休憩が取れていない」と相談されたときは、すぐにシフト表を見直していました。
具体的には
- 1人勤務の時間帯を短縮する
- 休憩時間に別のスタッフを配置する
- シフトの時間帯を変更する(6時間以内に収める)
- オーナーや店長が休憩時の店番に入る
良心的な店舗であれば、きちんと対応してくれるはずです。
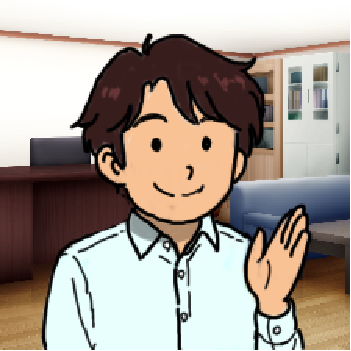
休憩がないまま長時間労働は違法の可能性も
6時間を超える勤務で休憩が取れない状態が続くのは、労働基準法違反です。
違法となるケース
- 8時間勤務で休憩が全くない
- 休憩時間中もレジ対応を求められる
- 「休憩なし」で時給が同じ(休憩分の時給が支払われていない)
私の経験では、悪質な店舗では「休憩時間」として給与から差し引いているのに、実際には休憩を取らせないというケースもありました。 これは明らかな違法行為です。
休憩削りが常態化している店は注意
以下のような状況が続く店舗は、労働環境に問題がある可能性が高いです。
要注意のサイン
- 毎回休憩時間が削られる
- 「忙しいから休憩なし」が当たり前
- 休憩中もレジ待機を求められる
- 店長に相談しても改善されない
- 他のスタッフも休憩を取れていない
このような状況が改善されない場合は、辞めたいと思った瞬間の一つとして、転職を検討することも選択肢の一つです。
私が店長として心がけていたのは、「スタッフがしっかり休憩を取れる環境こそが、結果的に店舗運営の安定につながる」という考え方でした。 疲れたスタッフは接客の質が落ち、ミスも増えるからです。
コンビニバイトで休憩を快適に過ごすコツ

バックヤードでの過ごし方
コンビニの休憩は、基本的にバックヤード(事務所や休憩室)で取ります。
バックヤードの一般的な設備
- 椅子やソファ
- テーブル
- 冷蔵庫(店舗による)
- ロッカー
私の店舗では、スタッフが快適に休憩できるよう、以下の環境を整えていました
- 清潔な休憩スペースの維持
- 冷暖房の完備
.jpg)
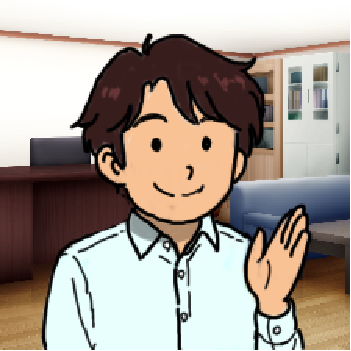
飲食・スマホ利用はどこまでOK?
休憩時間中の過ごし方について、ルールは店舗によって異なります。
一般的に許可されていること
- スマホの使用(SNS、動画視聴など)
- 飲食(持参した食べ物や店内商品を購入して)
- 読書や音楽鑑賞
- 軽い仮眠
店舗によって制限されること
- 店内商品の飲食(購入前提でもNG の場合)
- 大きな音を出す行為
- 店外への外出(短時間でも)
私の店舗では、休憩中に店内商品を買って食べることはOKとしていました。 むしろ、新商品を食べてもらうことで、お客様への商品説明に役立つという利点もありました。
「休憩中に買い物はできる?」という質問に対しては、基本的にOKですが、レジ対応が必要な場合は他のスタッフに頼むのがマナーです。
周囲に気を使いすぎないのが大事
新人スタッフによくあるのが、「休憩を取ると迷惑をかけるのでは」と遠慮してしまうことです。
私が店長として常に伝えていたのは、「休憩は権利であり、遠慮する必要はない」ということです。
休憩を気持ちよく取るためのポイント
- 休憩前に「〇〇時まで休憩いただきます」と声をかける
- 休憩明けは「ありがとうございました」と挨拶
- 他のスタッフの休憩時間も尊重する
- 休憩を理由に業務を中途半端にしない
休憩は体力回復のために必要不可欠です。 しっかり休んで、後半の業務に集中できる方が、店舗全体にとってもプラスになります。
まとめ:法律上のルールと実態を理解して働こう

応募前に確認するチェックリスト
コンビニバイトの休憩時間について、重要なポイントをまとめました。
休憩時間の法律ルール
- □ 6時間以下の勤務:休憩義務なし
- □ 6時間超〜8時間以下:最低45分の休憩
- □ 8時間超:最低1時間の休憩
- □ アルバイトにも完全に適用される
- □ 休憩時間は時給が発生しない
実際の現場での休憩
- □ 短時間勤務(4時間未満):休憩なしが一般的
- □ 4〜6時間勤務:15〜30分の休憩を設ける店舗が多い
- □ 6時間以上:45分〜1時間の休憩
- □ 1人勤務では取りづらい実態がある
- □ 深夜シフトは深夜2〜4時頃が休憩時間
休憩を取れないときの対処
- □ まず店長に相談してシフト調整
- □ 6時間超で休憩なしは違法
- □ 改善されない場合は労働基準監督署へ
- □ 常態化している店は転職も検討
休憩の過ごし方
- □ バックヤードで過ごすのが基本
- □ 飲食・スマホ利用は店舗ルールに従う
- □ 店内商品の購入・飲食は店による
- □ 遠慮せず権利として休憩を取る
法律と現場の実態を理解することが大切
コンビニバイトの休憩時間は、法律ではしっかり保護されています。 しかし、現場では「忙しい」「1人勤務」などの理由で、思うように休憩が取れないこともあるのが実態です。
私が20年以上の店長経験から学んだのは、休憩をしっかり取れる環境こそが、長く働き続けられる職場の条件だということです。
休憩をしっかり取れる環境で働くことの大切さ
休憩時間を軽視する店舗では、以下のような問題が起きやすくなります
- スタッフの疲労が蓄積し、ミスが増える
- 体調を崩して辞めるスタッフが増える
- 人間関係がギスギスする
- 結果的に人手不足が深刻化する
逆に、休憩をしっかり取れる店舗では
- スタッフの定着率が高い
- 接客の質が維持される
- 働きやすい雰囲気が生まれる
- 長期的に安定した運営ができる
これからコンビニバイトを始める方は、面接時に以下の点を必ず確認してください
- シフトごとの休憩時間
- 休憩を取るタイミング
- 1人勤務の頻度
- 休憩室の有無と設備
コンビニバイトの給料日やシフトの決め方と同様に、休憩時間も働く上での重要な条件です。 法律で保証された権利を理解し、しっかり休憩を取れる環境で気持ちよく働いてくださいね。
何かご質問があれば、いつでも「コンビニぐらし」でお待ちしています!
よくある質問(FAQ)

Q1:コンビニバイトは4時間勤務でも休憩はありますか?
A:労働基準法では6時間未満の勤務に休憩の義務はありません。4時間程度の短時間バイトでは休憩がないのが一般的ですが、店舗によっては10〜15分程度の小休憩を設ける場合もあります。
Q2:6時間以上勤務しているのに休憩を取れないのは違法ですか?
A:はい。6時間を超える労働には最低45分の休憩が必要です。継続して休憩が与えられない場合は店長に相談し、改善されないときは労働基準監督署へ相談することを検討してください。
Q3:休憩中に店内にいないといけませんか?
A:必ず店内に居る必要はありません。原則として休憩時間は自由に過ごせます。ただし店舗ルールで「外出不可」としている場合もあるため、事前に確認してください。
Q4:休憩時間にお客さんが来たら対応しないといけませんか?
A:休憩は労働時間に含まれないため、対応義務は基本的にはありません。ただし実務上は人手不足で呼ばれることがあり、その場合は店長と相談のうえ対応するケースが多いです。
Q5:深夜バイトの休憩時間はどうなりますか?
A:深夜でも労働時間に対する休憩のルールは同じです。来客の少ない時間に交代で仮眠や食事休憩を取るケースが多く、店舗によっては休憩室やリクライニングチェアを用意しています。











